共有持分を担保に融資を受ける、または住宅ローンを利用することはできるか?―共有持分の抵当権設定について―
共有持分を担保にして融資を受けたい場合や、住宅ローンを利用したい場合など、どうしたら良いのか?
結論から言えば、共有持分にも抵当権の設定が出来るので、持分だけを担保に融資を受けることは
可能です。
自分の共有持分だけであれば、抵当権を設定するのに他共有者の同意は不要です。では、共有持分の抵当権設定についてご説明します。
alt共有持分を担保に融資を受ける
1)抵当権とは何か
2)抵当権設定登記とは何か
1)自己の共有持分のみに抵当権を設定する場合は、他共有者の同意は不要
2)自己の共有持分の一部のみに抵当権を設定することはできない
3. 共有持分の抵当権の設定方法と抵当権設定登記にかかる費用について
1)共有持分の抵当権の設定方法
-債権者と金銭消費貸借契約を締結する
-抵当権設定契約を締結する
-法務局にて登記申請を行う
-登記事項証明書を債権者に提出する
2)抵当権設定登記にかかる費用
-登録免許税(登録料)
-司法書士に支払う報酬

1.抵当権とは何か
1)抵当権とは?
債権者(お金を貸す側)が融資する際に、債務者(お金を借りる側)の不動産を担保に設定できる権利のことを抵当権と言います。
住宅ローンの返済が滞るなど、いざというときの為に債権者は債務者の不動産を担保として設定できます。
抵当権の設定は住宅ローン融資の条件として求められる場合が多いです。
借り入れたローンの返済が滞った場合には、金融機関は抵当権を実行して不動産を競売にかけることができます。その配当金でローン返済に充当するのです。
抵当権を設定する金融機関を「抵当権設定者」と言います。
不動産担保ローンを返済する不動産購入者を「抵当権者」と呼びます。
抵当権設定義務があるのは抵当権者である購入者です。
2)抵当権設定登記とは何か
抵当権設定登記とは、第三者に対して、抵当権が付いた物件であることを示すために行う登記のことを言います。
抵当権設定登記をしていない債権者は、不動産を担保にしている事実を証明できないため抵当権を実行できません。
また、最初に登記した抵当権を「1番抵当」、次に設定登記した債権者の権利を「2番抵当」と言い、他の債権者よりも優先的に返済してもらうためにも抵当権設定登記を行います。
抵当権設定登記は、債務者と債権者の間で融資が実行されたその日に登記されます。
2.自己の共有持分のみに抵当権を設定するのは可能
共有持分を担保にして融資を受けた場合や、共有名義で住宅ローンを利用した場合など、共有持分に対して抵当権を設定することは可能です。
1)自己の共有持分のみに抵当権を設定する場合は、他共有者の同意は不要
共有不動産全体に抵当権を設定する場合は、共有者全員の同意が必要です。
しかし、自己の共有持分のみに抵当権を設定する場合は、他の共有者の同意は必要ありません。
他共有者の同意を得る必要がないため、自己の共有持分に抵当権を設定しようと考えている方もいると思いますが、ここでは注意点を確認しておくことが大切です。
2)自己の共有持分の一部のみに抵当権を設定することはできない
まず、不動産に抵当権を設定する場合、不動産の一部分のみに抵当権を設定することはできません。それは、不動産のどの部分に設定するかによって資産価値が異なるためです。
不動産に抵当権を設定する場合は、その一部分ではなく、持分全体に設定するということになります。
共有持分においても自分のもつ共有持分のうち、一部分だけに抵当権を設定するということはできず、対象の共有持分全体に抵当権が設定されます。
そこは不動産に抵当権を設定する場合と同様、共有持分の一部分のみに抵当権を設定することはできないということです。
自己の共有持分に抵当権を設定することは可能ですが、その場合には一部分にだけではなく、全体に設定しなければならないので注意しましょう。
alt費用について
3. 共有持分の抵当権の設定方法と抵当権設定登記にかかる費用について
1)共有持分の抵当権の設定方法
-債権者と金銭消費貸借契約を締結する
抵当権設定前にまずは、金融機関と金銭消費者貸借契約を締結します。
金銭消費者貸借契約とは、融資を受けた債務者が、将来的に一定の利息を付けて債権者に返済する契約のことです。
簡略化して、住宅ローン契約と呼ばれるケースもあります。
抵当権は金銭の融資をする契約ではないので、上記のように何かしらの契約を締結し、契約に定められている内容を履行できない場合に実行されるものです。
そのため、まずは抵当権を締結する前提となった金銭消費貸借契約を債権者(金融機関)と締結します。
-抵当権設定契約を締結する
金銭消費貸借契約を締結した後は同時に、抵当権設定契約を締結します。
抵当権設定契約とは、不動産や共有持分に抵当権を設定するという契約です。
抵当権設定契約には万が一、契約者の返済が滞り融資を回収できなくなった場合、債権者が抵当権を設定した不動産や共有持分を売却できる、その売却代金を返済に充てる旨などが記載されています。
-法務局にて登記申請を行う
登記書類の作成、申請は司法書士に依頼するのが一般的です。
抵当権設定契約を締結しただけで、抵当権の設定が完了するわけではありません。
抵当権を設定するには、設定登記に必要な書類を用意し、法務局にて登記申請を行う必要があります。
-登記事項証明書を債権者に提出する
登記の申請が完了した後は、登記事項証明書を取得し債権者に提出します。これにより、抵当権設定登記が完了したことが証明されます。
登記事項証明書とは、データ化された登記簿の内容を専用の用紙に印刷したものです。
2)抵当権設定登記にかかる費用
-登録免許税(登録料)
登録免許税とは、設定登記をする際にかかる税金のことです。
ローン額に対して0.4%乗じた金額が納税額になります。
-司法書士に支払う報酬
司法書士報酬の相場は2万円~10万円といわれています。
案件の規模によって変動するなど、依頼する司法書士事務所、地域などによって大きく相場は変動するため幅広い相場となっています。
金融機関が司法書士を選定しないと融資しないケースもあるので、司法書士費用は必要経費と考えておきましょう。
その他、印鑑証明書や全部事項証明書の発行手数料などで、1,000円前後の雑費が必要となります。

4. 共有持分に抵当権を設定した後について
自分の共有持分のみに抵当権を設定するのは、他の共有者の同意を必要とせず単独で行うことが可能です。
結果、自分の持分を担保に融資を受ける、もしくは住宅ローンを組むということができます。
しかしいくら単独で行えると言っても、後に他の共有者に迷惑をかける、もしくはトラブルに発展する可能性があります。
例えば融資や住宅ローンの返済が滞ってしまい、抵当権が実行され、自分の共有持分を手放すことになれば、見ず知らずの第三者が共有者になります。
その新しい共有者が、他の共有者の持分を買い取りたいと希望したとして、それを断れば共有物分割訴訟を起こされることも考えられます。
※共有物分割訴訟について、詳しくはこちらのページをご覧ください
https://xn--nckg3oobb8101c23ax2fstsxpylek.com/manabi/kotsu10.html
このような事例を考えたところ、事前に他共有者と相談してから共有持分に抵当権を設定することをおすすめします。
また詳細に応じて注意点がある為、詳しいことは是非、専門家に相談しましょう。
おすすめ不動産会社ランキング
-

株式会社中央プロパティー
95/100点

社長が専門家としてTVや雑誌で多数紹介。独自の入札方式で高値売却を実現。不動産鑑定士による調査報告書有り。
-

株式会社大正ハウジング
55/100点
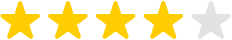
1995年設立の社歴のある買取専門会社。センチュリー21の加盟店。東京都内の交通広告でおなじみ。
-

一般社団法人 不動産あんしん相談室
50/100点

代表者が女性で相談しやすい雰囲気。一般社団法人。大阪エリアに強い。
-

株式会社蒼悠(港コンサルティング)
50/100点

関西エリアに強い大阪の不動産会社。年間の相談実績が200件超。無料の訪問査定有り(机上査定も対応可)。
-

株式会社チェスター
40/100点

相続税専門の税理士法人グループ会社。東京、横浜、大阪に支店あり
