共有者が海外にいる場合でも共有名義不動産は売却できる
共有名義不動産全体を売却するには、基本的に共有者全員の同意や立ち会いが必要です。
しかし共有者の1人が海外にいるなど、話し合いが難しい場合もあります。
共有名義の不動産を売却する際に海外居住の方がいる場合には共有者が日本に居住している場合と違った問題が生じます。
例えば必要になる書類に違いが生じ、その書類の取得方法も変わってきます。
共有者が海外に居住する場合でも共有名義不動産の売却は可能ですので、その際の方法についてご説明します。alt共有者が海外にいる場合の持分売却について
2.共有者が海外に住んでいる場合でも共有名義不動産を売却できる
1)海外からの帰国にあわせ直接本人が売却に立ち会える場合
2)本人が立ち会えず代理人専任の場合
3)海外居住の共有者も自己持分のみを売却できる
3.海外居住の共有者が不動産売却し利益が発生した場合は確定申告が必要
1)海外居住者の確定申告には納税管理人の選出が必要
2)売却した翌年に確定申告をする
1)共有持分を他の共有者が買い取る
2)遺言書で事前に不動産の相続人を指定しておく

1.共有名義不動産全体を売却する際は全員の同意が必要
共有名義で不動産を取得している場合、全ての共有者が近くにいるとは限らず中には仕事や結婚などで海外に住んでいる人もいると思います。
日本に住んでいる共有者の中には他の共有者が損をしなければ、無断で貸したり売却しても問題ないと思っている方もいるかもしれません。
しかし不動産が共有状態の場合、共有者は不動産に対する一部の行為が制限されるので注意が必要です。
不動産の使用や自己持分のみの売却、経年劣化に対する修繕といった保存は単独で行えますが、賃貸物件として貸し出す場合や、リフォームやリノベーションなどの改良は過半数の同意が必要で、共有名義不動産全体の売却や抵当権の設定などの処分も共有者全員の同意を得なくてはなりません。
そのためいくら一部の共有持分を有する1人が海外にいる場合でも共有者である以上は同意を得なければ無断で不動産全体を売却できないということを注意しなければなりません。
2.共有者が海外に住んでいる場合でも共有名義不動産を売却できる
1)海外からの帰国にあわせ直接本人が売却に立ち会える場合
共有者が海外にいても遠く離れた国ではない、都合に合わせて帰国できる状況にあれば不動産を売却する際に直接本人が立ち会うことが可能です。
直接本人が売却に立ち会える場合では、共有状態の不動産を売却する際の手順は一般的な不動産の売却と大きく違いはありません。
しかし、1点だけ大きく異なるのは売買契約の際に用意する必要書類です。
不動産売却では売主である共有者の住民票や印鑑証明書が必要になりますが、海外に住んでいて海外移住届を出している人にはこれらの書類がありません。
こういう場合は住民票や印鑑証明書の書類を準備できない代わりに、海外の日本大使館といった在外公館で在留証明書やサイン証明書を準備する必要があります。
在留証明書は在外公館のみで発行されており日本国内では発行できないので、日本に帰国する前に在留証明書とサイン証明書の準備をしておくことが必要です。
海外居住の場合は、日本国内で印鑑証明書を取得することは出来ないので印鑑証明書に代わるものとして、日本大使館でサイン証明書を発行してもらい、サイン証明書を印鑑証明書の代わりとして登記に使用します。
海外に居住する共有者本人が書類に自らサインしその書類に大使が本人のサインに間違いないことを記します。
サイン証明書を取得したい場合は、予め日本大使館にサイン証明書の申請書に使用目的等必要事項を記載し予約をします。
その後サイン日当日に大使館を訪れ必要書類にサインをして発行してもらいます。
海外の方が帰国することなく売買を行うことも不可能ではありませんが、日本で揃って売買契約をした方がスムーズですし、手続き上の問題も少なくてすみます。
ですが海外居住の方は簡単に何度も帰国ができないので、帰国より前の段階で売買の段取りを組むことが必要です。
こういったことをスムーズに行うためには前もって打ち合わせをすることがベストです。
最近ではZOOMで海外居住の共有者とお互いの顔を見ながら担当する業者を含めて打ち合わせも行えます。
帰国前に三者間でZOOM面談をして契約の内容、必要書類、費用、流れなどを打ち合わせ、帰国時期の中から売買契約日を決めておきます。
最近は、コロナウイルスのせいで帰国後に自主待機期間の要請がありますのでその期間を考慮した日程で売買契約日を決めていきましょう。
海外居住の共有者がいる場合には、どうしても手続き上で面倒な部分は出てきてしまいますが売買できないわけではありませんのであきらめないようにしましょう。
専門業者のアドバイスがあればよりスムーズに運ぶことができるでしょう。
2)本人が立ち会えず代理人専任の場合
不動産の売却に立ち会うためだけにお金を払ってまで帰国することに意味がないと考えている人もいるため、必ず共有者が不動産売却に立ち会うとは限りません。
しかし共有不動産全体を売却する場合は必ず共有者全員の同意を得なくてはならず、本人が立ち会えない場合は代理人を立てる必要があります。
海外に居住している共有者が帰国できず、代理人を立てて不動産の売却をする場合でも本人が立ち会う場合と同じく、在留証明書やサイン証明書が必要です。
そして本当に依頼を受けた代理人なのかを証明するために委任状が必要となります。
委任状の作成に当たりに決まった書式はありませんので、本人が望んでいない価格で売買が成立しないように代理人にどこまでの権利を付与するのかを明確に定めておくことが重要です。
委任状作成に不安がある方は委任状の作成、代理も含めて信頼できる弁護士や司法書士に相談し依頼しましょう。
3)海外居住の共有者も自己持分のみを売却できる
共有者全員が同意して売却する全部売却について説明しましたが、在留証明書、サイン証明書、代理権限委任状を用意できれば海外居住の共有者が自分の持分のみを売却する一部売却も可能になります。
持分のみの売却となると用途が限られるため、個人では一般的に買い手がつがず売却先は主に投資家か買取り業者になることでしょう。
しかし売主が国外居住で日本に住んでいないときは手間が増えるため購入を敬遠する業者も多いので注意しましょう。
alt確定申告
3.海外居住の共有者が不動産売却し利益が発生した場合は確定申告が必要
海外居住であっても日本居住の場合と同様に、売却によって利益が発生した場合は譲渡所得として計上されるため確定申告が必要になります。
つまり、どこに住んでいようとも日本国籍である以上は納税の義務があると考えられるので忘れずに確定申告を行いましょう。
譲渡所得と所得税は日本と同じ計算方法で算出します。
国内非居住者は日本に住所がないため、住民税は課税対象外です。
1)海外居住者の確定申告には納税管理人の選出が必要
海外居住者で日本国内に住所を持たない方が確定申告をする時、納税管理人を選任しなければなりません。
納税管理人は海外居住者に代わって日本の税務署へ確定申告書の提出をしたり税金を納めたり税務署からの連絡を受けたりする人のことです。
納税管理人は個人、法人どちらでも選任可能です。
親族などと関係が悪く納税管理人を頼めない場合には、会計事務所や税理士事務所を指定できます。
納税管理人を決めたら、その方の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出します。
届出書提出後は、納税管理人へ税に関する連絡、書類は届くので必要に応じて連絡を受けるようにしてください。
2)売却した翌年に確定申告をする
確定申告は、売却した翌年2月16日から3月15日までの期限内に共有名義不動産の売却で得た所得を計算して確定申告をおこない、所得税を納めることになります。
海外居住者が日本国内での所得をそのまま海外に持ち出して確定申告しないことを防ぐために海外居住者が不動産を売却するとき、その買主は購入代金から源泉徴収して納税しなければならない場合があります。
買主が個人であり買主の本人または買主親族の居住用であり共有者の持分に応じた売却価格が1億円以下の場合は源泉徴収の必要がありません。
不動産会社へ買取りを依頼することになったり、買主が不動産投資を目的として購入したりする場合には、支払価格の10.21%相当額が源泉徴収されます。
源泉徴収をして納税する義務は買主側にあるので、手続きについて心配する必要はありません。
ただし、海外居住者が受け取れる金額は譲渡価額に持分を掛けた金額よりも少なくなることに注意してください。

4.共有者が海外にいる場合に共有状態を解消する方法
1)共有持分を他の共有者が買い取る
不動産が共有状態にある場合は、日本に住んでいる共有者の1人が海外に住んでいる共有者の共有持分を買い取るという方法があります。
日本に帰国している間に話し合い、海外に住んでいる共有者の共有持分を取得します。
そうすれば不動産を一括で売却することになった場合に海外に住んでいる共有者は権利を失っているため、日本国内の共有者のみで売却を進めることが可能です。
海外に住んでいる共有者は共有持分を少しでも高く買い取ってもらえるので共有持分を手放すことに応じてもらえる可能性が高いです。
しかし日本に住んでいる共有者の1人が共有持分を買い取れるほどの資力があるケースに限られてきますので注意しましょう。
2)遺言書で事前に不動産の相続人を指定しておく
まだ不動産が共有名義でない場合に、遺言書で事前に不動産の相続人を指定しておくという方法があります。
例えば遺産が現金6,000万円、資産価値6,000万円の不動産、妻と子供2人の合計3人で遺産分割を行うとします。
妻が不動産、子供が現金を3,000万ずつ相続するような遺言書を作成しておけば、不動産が共有状態にならずに済むので売却時のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
他にも、妻が現金と不動産を半分ずつ日本にいる子供が不動産を半分、海外にいる子供が現金を半分取得するという選択肢もあります。
しかし共有名義にするとトラブルが起きやすいので注意が必要です。
5.共有者(外国籍)が自国に帰ってしまい連絡が取れない場合の対応
共有者の所在はわかるが連絡が取れない場合は「共有物分割請求訴訟」を利用します。
裁判所に共有物分割請求訴訟を提起し、裁定により共有名義を解消しましょう。
共有者が行方不明で連絡が取れない場合は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申し立て家庭裁判所の監督のもと、不在者の所在や居所がわかるまで代わりに財産を管理します。
共有名義を解消するためには不在者財産管理人選任の後、裁判所に不動産売却の許可を取る必要があります。
行方不明者の生死が7年以上不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをするという方法もあります。
失踪宣告をすれば、不在者は死亡したものとみなされるので、相続(遺産分割)という形で共有名義を解消できます。
共有者に外国人がいる場合のトラブルについて参考にしてみてください。
https://xn--nckg3oobb8101c23ax2fstsxpylek.com/manabi/kotsu14.html
おすすめ不動産会社ランキング
-

株式会社中央プロパティー
95/100点

社長が専門家としてTVや雑誌で多数紹介。独自の入札方式で高値売却を実現。不動産鑑定士による調査報告書有り。
-

株式会社大正ハウジング
55/100点
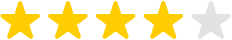
1995年設立の社歴のある買取専門会社。センチュリー21の加盟店。東京都内の交通広告でおなじみ。
-

一般社団法人 不動産あんしん相談室
50/100点

代表者が女性で相談しやすい雰囲気。一般社団法人。大阪エリアに強い。
-

株式会社蒼悠(港コンサルティング)
50/100点

関西エリアに強い大阪の不動産会社。年間の相談実績が200件超。無料の訪問査定有り(机上査定も対応可)。
-

株式会社チェスター
40/100点

相続税専門の税理士法人グループ会社。東京、横浜、大阪に支店あり
