土地活用は共有名義でも大丈夫!共有名義の土地を有効活用する方法
単独名義で土地を所有していれば自分で自由に活用したり時には売却したりできます。しかし自分の所有する土地が必ず単独名義とは限りません。
一般的に共有名義の土地活用は難しいと言われますが、共有名義であっても土地活用することは可能です。
自分の土地が共有名義だった場合にどのように活用していけばいいのか、土地を共有名義で利用する場合の上手な活用方法についてご説明します。
alt共有名義で土地活用をするメリット
1.共有名義で土地活用をするメリットについて
1)他の共有者の土地を買い取る必要がないのでコストが削減できるというメリット
共有名義の土地をそのまま活用すれば余計なコストがかからないというメリットがあります。
共有名義の土地を単独名義にするには他の共有者の持分を買取らなければなりません。
その際に共有者が多くなればなるほどかなり膨大な資金と労力が必要です。
他にもマンションなど建物を建てる土地活用では、建物の登録免許税や不動産取得税などの一定の自己資金が必要となります。
また建築費についても多額の資金が必要になるので、単独名義に変えるためにあまり高額な費用がかかってしまうと建物を建てる段階になって自己資金がなくなってしまう可能性があります。
共有名義のまま土地活用をすれば土地活用に資金を回すことができ、建物を建てる段階まで自己資金を十分に残しておくことができます。
共有名義のままの土地活用の方が単独名義よりも現実的な方法といえます。
2)広い土地をそのまま活かせるというメリット
共有名義のまま土地活用を行うと、土地をそのまま活かせるというメリットがあります。
共有名義の土地は買取りだけではなく分割することで単独名義に変えることもできる分筆という方法があります。
分筆とは、土地を共有名義者の人数で分け合いそれぞれが単独名義を持つ方法です。
与えられた土地を分け合えば単独名義で土地を活用し、他の持分の買取りにかかる費用も発生しないためコストを抑えることができます。
しかしこの方法にも問題はあります。
土地はそのすべてが平等の価値を持っているとは限りません。
分筆の仕方によっては間口の狭い土地や不整形な土地も発生してしまい、分筆することで逆に土地の価値を落としてしまうこともありますし、傾斜が激しい崖地や地盤が不安定な箇所など場所によって土地の価値も変わります。
また土地は一般的には広い方が用途の多様性が生まれ好まれます。
土地が広ければ賃貸マンションや介護施設のような幅広い土地活用も考えられますが、分筆を行って土地を分割してしまうと個人名義にはなりますがそれぞれが活用できる土地の面積は小さくなるため土地活用の選択肢が限られてしまいます。
広い土地ほど価値があるので、もし共有地が広い土地の場合は分筆はせずにそのままにした方が、良い土地活用をできるケースが多いです。

2.共有名義の土地の3つの権利形態について
1)「共有」「区分」「借地」の3つの権利形態
-「共有」;共有土地に建てた建物の管理割合を土地の割合で管理する方法
共有名義の土地活用では建築後の建物を共有で持つことが考えられます。
共有はその土地に建てた建物の管理割合を土地の割合で管理する方法で3つのなかで最もシンプルな方法です。
例えばAが土地全体の50%の所有権、Bが30%の所有権、Cが20%の所有権を持っている場合、建物の建築費用も、Aが50%、Bが30%、Cが20%ずつ出し合うことで建物の持分割合も土地の所有権割合も同一にすることで土地の所有権の比率と建物の所有権の比率を合わせるのが共有という管理形態です。
土地も建物も全て各共有割合が同じでもっとも単純なケースになります。
土地活用によって収入が入ってくる場合も、このケースだと全体の半分がAの利益となるので多く収益を得たいと考えている人は所有権の割合を多くするようにしましょう。
-「区分」;建物を区分ごとに分けて所有権を得るという方法
区分とは、建物の一部を独立した所有権の対象とし区分ごとに分けて所有権を得るという方法です。
身近な例としてはマンションが区分所有建物になります。
区分というのは主に階層で利用されることが多いです。
マンションは共有で土地の所有権を持っていますが、部屋は独立した単独所有となっています。
建物を区分とする共有名義の土地活用の場合では、例えば、A・B・Cの3人で3分の1ずつ土地を共有している場合、6階建ての建物を1~2階はA、3~4階はB、5~6階はCというような分け方をします。
共有の管理形態と異なる点は階層によって独立した単独名義であるという点です。
共有の場合、所有権の割合のみが決まっているためリフォームなどを行う際は共有名義の人全員に許可を得る必要がありますし、その時にかかる費用も、所有権の割合で折半して支払う必要があるため自分単独で行動をすることはできません。
しかし区分所有は独立した単独の所有権であるため、マンションのように区分所有者が自由に売買やリフォームを行うことが可能です。
この場合の家賃収入はフロアによって分けるのが一般的なので、建てる建物によっては階層によって価値が異なるかもしれませんので共有名義人同士でよく話し合う必要があります。
-「借地」;土地の所有権の割合を決め、建てた建物を一人の単独所有とする方法
※この場合の借地は「自己借地権」のことを言います。
共有名義の方々が全て土地活用に積極的ではない時におすすめなのがこの方法です。
借地という方法は、土地の所有権の割合を決め、建物を建て建物名義をこの建物の土地活用を行う人物一人の単独所有とする方法です。
土地は他の共有名義者が所有権を持っているため、完全に単独所有というわけにはいきませんので借地権を設定し一定額を土地の使用料(地代)として他の共有名義者に支払うことになります。
例えばA・B・Cの3人が3分の1ずつ持っている共有地で、Aだけで土地活用を行いBとCへは借地料を支払う方式です。
Aが全て土地を利用したい場合、借地権を設定すればAは土地全体を買わなくても全て土地を利用することはできます。
B・Cには地代を支払う必要はありますが建物は全てAの単独所有として活用することができるのです。
2)それぞれの権利形態でのメリットとデメリットについて
-「共有」で管理した場合
・家賃の差がなくなるというメリット
一棟の建物の所有権を決められた割合ずつ持つことによって、建物を共有で管理でき、共有者間で家賃の差がなくなり平等な運営ができるというメリットがあります。
マンションの土地活用をした場合など階層によって薄暗くて人気のない部屋や、角部屋で日当たりも良く人気のある部屋などがあります。
共有で管理した場合、その日当たりの悪い部屋でさえも所有権の割合に基づいて管理を行うことになるため、入居者が決まりやすい部屋のメリットと決まりにくい部屋のデメリットを共有者全員が平等に受け不平等が一切生まれず家賃収入に差が生まれないのです。
・一元的な運営ができるというメリット
共有は、建物を一元的に運営きるというメリットがあります。
オフィスビルを運営したとして、テナントは借りたい面積が1フロアのみとは限らず、2フロアだけ、もしくは3.5フロア(3フロア+半フロア)で借りたいなど、様々な要望があります。
オフィスビルを区分所有としてしまうと入居者が他の区分所有者のフロアにまたがって借りたいとなったとき、不都合が生じてしまうことがあります。
フロア管理者それぞれがテナントの貸し出しの判断を行うので、一方がよくても一方がダメだとフロアを貸し出すことができなくなり、土地活用がうまくいかないことが考えられます。
これが共有名義だった場合は全てのフロアの所有権を持っているため、一元的な運営を行うことが可能です。
オフィスビルや一棟貸のような土地活用は建物を区分で分けるのではなく、一元的に運営した方が貸しやすくなります。
・自由に意思決定できないというデメリット
共有不動産は全体での売却や修繕など単独で自由に意思決定できないというデメリットがあります。
共有物件は他人に賃貸する、賃貸借契約を解除する時などは共有者の過半数の同意が必要となりますし増築や建替え、全体売却などは共有者全員の同意が必要です。
・相続で共有者がさらに増える可能性があるというデメリット
建物を共有すると2次相続、3次相続で共有者がさらに増えてしまうというデメリットがあります。
共有物件のデメリットは意思決定のしにくさにあり、共有者が増えれば増えるほど難しくなっていきます。
全員が持分比率に関係なく平等に物件に対する所有権を持っているため共有名義者が多すぎると収集がつきません。
-「区分」で管理した場合
・売却しやすいというメリット
マンションのような区分所有物件は将来的に売却しやすいというメリットがあります。
区分を所有していると、自分が所有しているフロアに関しては自由に売却を行うことができます。
この手放しやすさは、非常に魅力的で市場性を高める要因となっています。
土地活用は常にうまくいくとは限りませんので一定の収益を望めない場合に見限ることも必要です。
その際に共有で管理している物件だと全体を売却する際は全員の同意が必要になるため、他の共有者がまだ土地活用の見込みがあると判断すれば売却することができません。
区分所有は将来的に売却したいと思えば他の共有者の同意を得ることなく自由に売却できるというメリットがあります。
・意思決定が容易だというメリット
区分所有は、区分の部分に関しては1人の単独所有であるため意思決定しやすいというメリットがあります。
リフォームや売却など、物件に関してありとあらゆる意思決定が容易というのもメリットです。
区分所有であれば、それぞれの所有者の工夫次第で、保有している区分の収益力を上げることができます。
売却しやすい、維持管理もしやすいという点に関しては、共有よりも区分の方がメリットはあるといえます。
・管理規約が必要となるデメリット
建物を区分で所有するとなると、トラブルを避けるために管理規約が必要となってきます。
この管理規約というのは、共用部分の管理をどのようにするか定めたものです。
区分所有の建物は、部屋の専有部分は単独所有となりますが、廊下やエレベーター、階段等の共用部分は共有で保有することになります。
エレベーターのメンテナンス費用、管理には清掃等の定期的な費用も発生します。また、外壁塗装や屋上防水の貼替等、大規模修繕に備えて修繕積立金も積み立てていく必要があります。
いわゆる普通の分譲マンションに管理規約があるように、区分所有する場合には、マンションで行っているようなことを全て作り上げていかなければなりません。管理のルールや修繕積立金の額等をしっかりと決めておきましょう。
・所有割合の調整が必要となるデメリット
区分で建物を持つ場合、最終的に所有権割合の調整が必要となるケースが多いです。
建物には、資産価値の高いところと低いところがあるため、最終的には各区分の資産価値を計算して割り振る必要がでてきます。
例えば資産価値を50%ずつ割り振ろうとすると、Aは1階と2階の2フロア、Bは3階から5階までの3フロアを割り当てることで資産価値として50%ずつ持つことができるようなケースもあります。
区分所有の建物は単純に面積だけで割り振ってしまうと元々の土地の共有持分の資産価値と同じにはならないため、建物が竣工した後に所有割合の調整が必要となってきます。
-「借地」で管理した場合
・自分一人で意思決定ができるので土地活用を推進しやすいというメリット
単独所有で一部を借地とする場合、土地活用を推進しやすいというメリットがあります。
基本的には1人で土地活用するのと同じであるため、全ての意思決定を1人でスムーズに行うことができます。
共有の場合、ある共有者が土地活用を推進したいと思っている部分でも、他の共有者が土地活用をする余力がなく反対するようなケースも生じます。
借地であれば、土地活用をしたい人だけがすれば良いので、土地活用をスムーズに推進できます。
さらに、地主に徹する共有者は労せずに地代収入を得ることができますので借地は他の共有者の同意を得やすいです。
収入に関しても、建物の所有権を100%持つため土地活用する人は収入も大きくなります。
・地代が発生するというデメリット
借地による土地活用は、地代が発生するため、土地建物の完全所有による土地活用よりは収益は若干劣ります。
借地料は一般的に土地の固定資産税の3~4倍程度を目安とすることが多いです。
借地料は当事者の合意で決めれば良いのですが、例えば固定資産税と同額程度の地代しか支払わないと借地ではなく使用貸借とみなされてしまいます。
使用貸借とは無償でおこなう貸し借りのことで、借主の立場は非常に弱いものです。
具体的には、地主が土地を返して欲しいと言えば、建物を取壊して更地返還しなければいけなくなります。
借主の地位を強固なものにするには、相応の地代を支払う必要がありその一つの目安が固定資産税の3~4倍です。
相応の地代を支払えば、建物所有を目的とした借地権として認められ、借地借家法により借主の立場が保護されます。
alt共有名義の土地を有効活用するには?
3. 共有名義の土地を有効活用するには?
共有名義の土地を有効活用するには売却し売却益をそれぞれの所有持分に応じて分配し、まとまった資金を手にする方法がありますが、その他の方法もいくつかご紹介します。
1)マンションやアパートの賃貸物件として運用する
共有土地にマンションやアパートを建設し運用すれば月々の収入を得られます。
賃貸物件の運用がうまくいけば出資した額を回収し利益を得られます。
しかし賃貸物件が駅から遠いなどの場合は入居希望者が減るため家賃収入も少なくなってしまい思ったように収益をあげられないかもしれません。
賃貸物件の運用には固定資産税や所得税といった税金、管理費用も必要ですので共有土地に賃貸物件を建てる方法はリスクが高いと言えます。
2)コインパーキング、月極駐車場として貸し出す
初期投資にかかる費用が少なく管理も容易なコインパーキングや月極駐車場を運用するのも一つの方法です。
都市部や住宅街に近い土地であれば高い利益が見込めます。
もし将来的にアパートを運用する、もしくは売却する予定がある場合も用途変更はスムーズにできます。

4.共有名義の土地を活用する際の注意点
1)共有土地の活用には共有者の同意が必要なため意思決定が難しい
共有土地は共有者同士で利害関係が対立しやすく、共有土地の扱いを巡ってトラブルになりがちです。
共有者全員が土地に対する権利をもっているため、土地を活用するには基本的に共有者全員の同意を得なければなりません。
2)等価交換でも検討してみる
共有名義の土地活用をする場合、等価交換も駆使すると活用しやすくなります。
等価交換とは完成した建物と土地の所有権を等価で交換する方法です。
例えば、1億円の資産価値のある土地を、AとBが50%ずつ所有しているケースを考えます。
その土地の上にAが単独で1億円の建物を建てます。
このままだと、Aは土地の50%をBから借地している状態です。
そこで、Aの建物の25%(2,500万円)をBの土地の25%(2,500万円)と交換しAは25%の土地所有権を得て25%の建物所有権をBに譲ります。
すると、Aは土地と建物を75%ずつ持ち、Bは土地と建物を25%ずつ持てるようになります。
Bは持分こそ減りますが何もせずに25%分の土地建物の収益物件を得ることができます。
仮に、共有者の一人が土地活用は面倒だけど、ちょっとでも分け前を欲しいとなった場合は等価交換なら共有者を納得させやすいです。
3)運用の後からでも共有状態は解消すべし
共有名義でも土地活用はできますが、建物を運用した後からでも可能であれば共有状態は解消すべきです。
共有者が個人同士の場合、共有不動産は時間が経つと2次相続3次相続が発生し共有者が増えていく現象があります。
そのため土地を有効活用する為には、共有者の相続が始まる前に単独所有とする事が何よりも大切です。
おすすめ不動産会社ランキング
-

株式会社中央プロパティー
95/100点

社長が専門家としてTVや雑誌で多数紹介。独自の入札方式で高値売却を実現。不動産鑑定士による調査報告書有り。
-

株式会社大正ハウジング
55/100点
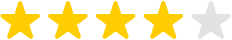
1995年設立の社歴のある買取専門会社。センチュリー21の加盟店。東京都内の交通広告でおなじみ。
-

一般社団法人 不動産あんしん相談室
50/100点

代表者が女性で相談しやすい雰囲気。一般社団法人。大阪エリアに強い。
-

株式会社蒼悠(港コンサルティング)
50/100点

関西エリアに強い大阪の不動産会社。年間の相談実績が200件超。無料の訪問査定有り(机上査定も対応可)。
-

株式会社チェスター
40/100点

相続税専門の税理士法人グループ会社。東京、横浜、大阪に支店あり
